「コーヒーは好きだけど、飲むと体調が悪くなるかも…」そんな悩みを抱えていませんか?
カフェインは私たちの脳や体に活力を与えてくれる一方で、敏感な人にとっては、動悸、不眠、胃の不調などを引き起こす原因にもなり得ます。
実は、カフェイン感受性には個人差があり、「コーヒーを飲みたいけど体がついていかない」という方は決して珍しくありません。
私もその一人で大好きなコーヒーとの付き合い方を模索中です。
この記事では、カフェインが体に与える影響について解説するとともに、カフェインに敏感な方でもコーヒーを楽しむための工夫や選び方を考えてみたいと思います。
「コーヒー好き」のあなたが、無理せず毎日の一杯を楽しむヒントになりますように。
1. カフェインに弱いってどういうこと?
まず、カフェインに対する反応は人それぞれです。
1日にコーヒーを何杯飲んでも平気な人もいれば、1杯飲んだだけでも夜寝つきが悪くなる人もいます。
遺伝や体質によってカフェイン耐性には個人差があり、肝臓でのカフェイン分解速度が遅い人は、カフェインが体に長時間残りやすいと言われています。
カフェインによる不調の症状例:
- 動悸
- 不眠
- 胃の不快感
- 頭痛集中力低下など
カフェインの摂取上限は、一般的には1日400mg以下が安全とされていますが、これよりずっと少量でも上記のような影響を受ける人は“カフェインに弱い”と言ってもいいかもしれません。
| カフェイン摂取の一日の目安量 | 提唱している機関名 | |
|---|---|---|
| 子供 | 2.5mg/kg(体重40kgで約100mg) | カナダ保健省 |
| 4-6歳 7-9歳 10-12歳 | 45mg 62.5mg 85mg | |
| 健康な成人 | 400mg | カナダ保健省 |
| 妊婦 | 300mg 300mg 200mg | カナダ保健省 オーストリア保健・食品安全局(AGES) 英国食品基準庁(FSA) |
カフェインに強い人でも注意が必要です。
下の表は、100mlあたりのカフェイン含有量を表したものです。
コーヒーのカフェイン含有量は60mg/100ml。
1杯200mlとしたらカフェインは120mgなので、1日に3〜4杯以上飲むと「1日の目安量」を超えることになります。
また、コーヒー以外にも日常生活の中でカフェインが含まれているものは多いので、例えカフェインに強くても気をつけなければ「目安量」を超えてしまいます。
| 飲み物・食べ物の種類 | カフェインの量 | 抽出方法(1杯あたりの液量) |
|---|---|---|
| コーヒー ドリップ式 インスタント (顆粒製品) 缶コーヒー・コーヒー飲料* | 60mg/100ml 57mg/100ml 10未満-90mg /100mg | コーヒー粉末 10g/熱湯 150ml インスタントコーヒー 2g/熱湯 140ml 1本あたり 165-480mg(製品による) |
| 玉露 | 160mg/100ml | 茶 10g/60℃の湯 60ml, 2.5分 |
| 紅茶 | 30mg/100ml | 茶 5g/熱湯 360ml, 1.5-4分 |
| 煎茶 | 20mg/100ml | 茶 10g/90℃の湯 430ml, 1分 |
| ほうじ茶 | 20mg/100ml | 茶 15g/90℃の湯 650ml, 0.5分 |
| ウーロン茶 | 20mg/100ml | 茶 15g/90℃の湯 650ml, 0.5分 |
| ココア | 7mg/100ml | ピュアココア 5g/牛乳 140ml |
| 麦茶 | 0mg | 茶 50g/湯 1500ml, 沸騰後5分放置 |
| エナジードリンク | 32-300mg/100ml | 1本あたり36-150mg(製品による) |
| ミルクチョコレート | 25-35mg/100g | |
| ハイカカオチョコレート | 70-120mg/100g |
参考「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」文部科学省
「カフェインの過剰摂取について」農林水産省
「高カカオをうたったチョコレート」厚生労働省
*アサヒ飲料、キリン、サントリー、伊藤園の各ホームページ商品情報
2. カフェインの体への影響
カフェインの体への影響を科学的な視点を交えてまとめていきたいと思います。
そもそもカフェインとは?
カフェインはメチルキサンチン類(アルカロイド)に属する化学物質で、苦みを持ち、もともとは植物が昆虫に食べられないようにするために作られた物質のひとつと考えられています。
カフェインは比較的熱に強く、強い焙煎の場合に微量が昇華して失われる以外は単一の成分として焙煎後もほとんどが残ります。
脳内物質のアデノシンは、ドーパミン、ノルアドレナリン、グルタミン酸といった興奮性の神経伝達物質の放出を抑制します。カフェインはアデノシンの抑制を抑えるので、間接的に脳を興奮、覚醒させます。カフェインの感受性には個人差があり、アデノシン受容体遺伝子の違いに基づくと考えられています。
ポジティブな効果
カフェインは上手く生活に取り入れることでポジティブな効果を発揮してくれます。
覚醒効果:眠気を抑え、注意力・集中力を向上させる。
カフェインには覚醒効果があり、物事への注意力と集中力が増します。「眠気覚ましに〜」と言われているのはこのためですね。
カフェイン摂取直後に認知機能テストを実施すると反応時間が短縮し、注意力や集中力などの認知機能が高くなります。カフェインによる計算能力の向上は摂取後30分くらいから現れ、1時間後にピークとなり、その後、数時間効果が続きます。〜 カフェインの継続的な摂取量が多いほど反応時間が短く、言語記憶などの成績がよいことが示されています。
ネスレ インタビュー記事『カフェインと脳の働き』(東京福祉大学 短期大学部 教授 栗原久)
運動能力の向上:スポーツ選手やジムでトレーニングする人など。
2018年に国際オリンピック委員会が公表した栄養サプリメントの合意声明(コンセンサス・ステートメント)では適度なカフェインは、「パフォーマンスを改善する」ための十分~強力な科学的根拠をもつ成分と評価されています。
運動前にコーヒーを飲む習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか?
| IOCによる例示 | 科学的根拠 | 成分と科学的根拠 |
|---|---|---|
| アスリートが補給を必要とする微量栄養素の例 | あり | ビタミンD、鉄、カルシウム |
| パフォーマンスを改善するサプリメント (特定のシナリオでの実施) | 十分~強力 | カフェイン、クレアチン、硝酸塩、β-アラニン、重炭酸ナトリウム |
| アスリートの免疫力をサポートする栄養補助食品 | 中程度 低い〜中程度 限定的 裏付けなし | ビタミンD、プロバイオティクス、ビタミンC(予防)、亜鉛(治療) 糖質、ウシ初乳、ポリフェノール(ケルセチンなど) グルタミン、カフェイン、エキナセア、ω3PUFA ビタミンE、β-グルカン |
| トレーニング、回復、筋肉痛、怪我の管理に 役立つ可能性があるサプリメント | 裏付けあり 裏付け不十分 | クレアチン(除脂肪体重と筋力増加、トレーニング適応改善)、 β-ヒドロキン-β-メチル酪酸HMB(除脂肪体重・筋力に小さい効果) ロイシン代謝物(筋力増加、筋肉損傷低減)、ω6脂肪酸(筋回復)、ビタミンD(筋回復)、 抗炎症サプリ(筋肉損傷抑制) |
カフェインには運動機能への作用もあります。
1500m走3回の平均タイムを比べた英国の研究では、コーヒー(カフェインあり)を飲んだ場合の方が、カフェインレスコーヒーを飲んだ場合よりも約3秒速くなるという結果でした。カフェインは2004年まではドーピング禁止薬物に指定されていました。
「注意力・集中力の向上(75mg以上摂取)」や「持久運動パフォーマンスの向上(運動1時間前に3mg/kg体重摂取)」「持久運動時の主観的労作の軽減(同4mg/kg体重)」はヨーロッパでは科学的根拠が十分にあると見なされ、ヘルスクレーム(食品での機能性表示)が認められています。
ネスレ インタビュー記事『カフェインと脳の働き』(東京福祉大学 短期大学部 教授 栗原久)
ネガティブな効果
カフェインの代表的なネガティブな効果です。特にカフェインが弱い人は注意が必要です。
睡眠の質の低下
睡眠についてですが、カフェインを就寝前に摂取すると、入眠時間がやや長くなり、眠りが浅くなることがわかっています。
カフェインが睡眠に悪影響を及ぼすことはよく知られている。例えば、成人では、100 mg 以上のカフェイン摂取は睡眠潜時の延長、睡眠時間の短縮を引き起こすことが報告されている(Landolt et al., 1995)。一方、100 mg 未満では睡眠に対して著しい影響を及ぼさないという報告もある(Dorfman and Jarvik, 1970)。しかし、感受性の個人差を考慮すると、より少量のカフェインでも、睡眠に悪影響が生じると考えるべきである。
栗原 久『日常生活の中におけるカフェイン摂取-作用機序と安全性評価-』
不安やイライラ
大量のカフェインは不安を誘発する可能性があります。カフェインに弱い人は少量でも注意が必要です。
大量(400~500 mg 以上)のカフェインは、不安障害患者だけでなく、健常者でも不安を誘発することが知られている(Nawrot et al., 2003; Childs and de Wit, 2006)。Nickell and Uhde (1994)は、低用量のカフェイン(3 mg/kg:200 mg 相当)でも不安を誘発しうることを報告しているが、この臨床実験は経口摂取ではなく静脈投与なので、結果をそのまま日常生活における影響評価に利用するのには不適である。
栗原 久『日常生活の中におけるカフェイン摂取-作用機序と安全性評価-』
離脱症状の頭痛など
継続してカフェインを摂取していた人が突然やめると離脱症状が出ることがあるようです。
カフェイン(1日200mg、2週間以上)を継続的に摂取している人が、摂取を突然中止すると離脱症状(頭痛、注意力の低下、眠気など)がみられることが知られています。離脱症状の頭痛は、カフェイン摂取中断後24時間以内に出現しますが、約100mgのカフェイン摂取ですぐに消えます。また離脱症状自体もカフェイン摂取をやめると7日以内に消えるので、生活に対するマイナス効果は非常に少なく、社会的な問題が起こることは、ほとんどありません。カフェインを数日にわたり徐々に摂取を減量すれば、こうした症状は起こりません。
ネスレ インタビュー記事『カフェインと脳の働き』(東京福祉大学 短期大学部 教授 栗原久)
3. 個人的視点
カフェインに弱い私がカフェインについて感じることです。
生産性は上がるが安定感や余裕は減る
コーヒーを飲んでカフェインを摂ると、眠気は覚めるし集中力も上がって生産性は上がります。「気がついたら何時間もぶっ通しで作業していた」なんてこともあるし、もっとできる気がする。
一方で、生活の安定感や余裕は減ると感じています。
忙しく次々と物事をこなしてしまい最終的には逆に疲れてしまったり。
私の高校時代にこんなエピソードがあります。
私は厳しい練習で有名な部活動を乗り越えるために栄養ドリンクをよく飲んでいました。飲んだ時は疲労感を感じず頑張れるのですが継続していくうちに栄養ドリンクを飲まないとやってられないという状態に。

これではダメだと思い使用を控えるようになりましたが、この時の私の体は栄養ドリンクで体に鞭を打って無理やり働かせてしまっていたのだと思います。
『疲労感』は体を休ませるためのサインのようなものなので、それを感じづらくさせるカフェインには注意が必要だと学びました。
持続可能的に仕事をするために、生産性と体の調子のバランスが大事だと思います。
カフェインに強くなることはない
カフェインの成分に耐性がつくことがあるようですが、根本的な遺伝子レベルでのカフェインの強さは変わらないようです。
私の場合、コーヒーを久しぶりに飲んだ時は、ガツンと脳に来るくらい覚醒モードになるのですが、それから継続して飲んでいくと最初ほどのインパクトは感じなくなります。
「カフェインに強くなったのかな」と思いますが、知らぬまに疲労が溜まっていたり睡眠が浅くなっていたりと、その後コーヒーを絶ったときに本調子ではなかったことを認識します。
私は普段からコーヒーの量や飲む時間は気にして調整しているつもりですが、つい好きなコーヒーを飲んでいるうちに量や頻度が増えてしまうことが多々あり、毎回反省しているところです。
遺伝子レベルでカフェインに強くなることはないと思うので、自分の体質に合ったカフェインとの付き合い方だ大切だと痛感しています。
4. カフェインに弱くてもコーヒーを楽しむ方法
カフェインに弱くてもコーヒーを楽しみたい!
そんな私と同じような人のためにできることを考えてみます。
① デカフェを活用する
普段のコーヒーをディカフェにするだけでカフェインの摂取量を大きく減らすことができます。
ディカフェ(デカフェ)とは、カフェインを除去したコーヒーのことを指します。現在、欧米では市場の約20%を占めるほど人気があり、日本でも健康志向の人を中心に徐々に広まっています。
毎回ではなくても、疲れが溜まっているときや午後や夕方以降など、普段のコーヒーをディカフェに変えることでカフェインによるデメリットを少なくすることができます。
最近ではスペシャリティコーヒーのディカフェの商品が出てきているため、カフェインのデメリットを避けたい人でも美味しいコーヒーを飲む選択肢ができるようになっています。
ただし注意点もあります。
ディカフェでも、カフェインが完全にゼロではないということです。
同じような言葉でカフェインレスという言葉もあります。
カフェインレスコーヒーは、カフェインを90%以上除去したコーヒーのこと。
どちらもカフェインが大幅に除去されていますが、「カフェインが含まれていない」という意味の『ノンカフェイン』ではありません。
デカフェやカフェインレスは、カフェインに過敏になっているときやカフェインフリーで生活したいときには100%おすすめできるわけではありません。
ディカフェを活用してカフェインを減らす!
② エスプレッソで飲む
1日のカフェイン量を調整するために飲む頻度や飲む量を減らすのがまず考えられることですが。
私がおすすめしたいのは、『エスプレッソショット』でコーヒーの味を楽しむことです。
近年コーヒーが好きなった人は、豆本来の複雑な味や香りに魅了されたからではないでしょうか?
エスプレッソは濃縮されたコーヒーの味を少ない量で最大限楽しむことができます。
エスプレッソの気になるカフェイン量ですが、100mlあたりは以下になります。
- ドリップコーヒー:60 / 100ml
- エスプレッソ:200/ 100ml
エスプレッソの方が断然多いですが、カップに入れた1杯計算だと以下になります。
- ドリップコーヒー:120mg/ 200ml
- エスプレッソ:60mg/ 30ml
エスプレッソは容量30〜60cc程度のエスプレッソカップに入れて飲むため、1杯あたりのカフェインの摂取量はエスプレッソの方が少なくなります。
エスプレッソはただ苦いだけと思っていませんか?確かに一昔前まではそうだったかもしれません。
でも今はスペシャリティコーヒーの台頭に伴い、エスプレッソも変わってきています。
深煎りの苦味が強い豆を使うのではなく、浅煎りで酸味が美味しい豆を使うことで酸味や旨みが凝縮され脳にガツンと感じるようなジューシーなエキスになります。単純に豆本来の美味しさを味わいたい人にとってピッタリの飲み方といえます。
エスプレッソは、豆本来の味や個性を味わえて、カフェインはドリップコーヒーより少ない
あなたの街のスペシャリティコーヒーに力を入れているお店やエスプレッソが得意なお店を探してみてください。美味しいエスプレッソショットと出会えることを願ってます。
難点はエスプレッソマシンがないと飲めないことですね。
私の現状ではお店に行くしかエスプレッソを飲む手段はないです。
しかし、自宅でもエスプレッソを楽しめるエスプレッソメーカーがあるようです。
私はここら辺が気になっています。
エスプレッソにチャレンジ!
③ 時間帯に注意する
カフェインに感受性の高い方は、睡眠に気を使うならば夕食以降はカフェイン摂取を控えた方が良いでしょう。
できるならコーヒーのイベントは午前中に済ませる方がベターです。
カフェインの半減期は人によって2-8時間と言われています。
そしてこれも半減する時間なので体内から完全になくなる時間はもっとかかると推測されます。
あとは自分の体で実験してみるしかありません。
何時までにコーヒーを飲めば睡眠に支障がないか。
私はその結果、今のところ14時以降はコーヒーを飲まないようにしています。
自分の体のカフェインの反応を見ながらカフェインを摂る時間を調整しましょう。
睡眠に支障が出ない時間を把握する!
④ 牛乳や豆乳を加える
「エスプレッソショットで飲む」と同じですが、ドリップコーヒーで飲むよりもカフェイン量は少なく、ミルクと一緒に飲むことでカフェインの吸収を緩やかにできます。
あとは気休め程度かもしれませんが、コーヒーと一緒に水を飲むのもいいかもしれません。
コーヒーの利尿作用で体の水分が失われがちなので、意識して水分補給してあげることも大事です。
他の食べ物や飲み物と一緒に摂取する
⑤ ノンカフェインデーを作る(飲む頻度を減らす)
カフェインに弱いけどコーヒーが好きな人は、ノンカフェインデーやノンカフェインウィークを作るのをおすすめします。
自分の体調と相談することが大事。
疲れている体にカフェインを入れても後々さらに疲れるだけ。
体調に問題がなくコーヒーのメリットを享受したいときに飲むようにしましょう。
コーヒーは嗜好品なので必需品になってはいけないと思います。
体調が万全でない時はカフェインを摂らない
5. カフェインを摂りすぎてしまった。早く排出するには?
注意していても、ついカフェインを摂りすぎてしまうこともあります。
そんなときの対処法です。
- 適度に水を飲む
- 水分を積極的に摂りましょう。体内のカフェイン濃度を薄め、排出してくれる助けになります。(がぶ飲みはダメ)
- カリウムやマグネシウムを摂る
- カフェインはカリウムやマグネシウムを排出してしまいます。バナナやキノコや海藻などミネラルを多く含む食べ物を意識して食べましょう。私はサプリメントで効果がないか実験中です。
- 軽い運動をする
- 軽い運動をして代謝を促進させましょう。

6. まとめ:コーヒーと上手く付き合っていきましょう!
体質的にカフェインに弱い人は、コーヒーと上手く付き合っていくかそもそも摂取しないかしかありません。
私も模索中ですが、コーヒーを楽しむ方法はいくつもあります。
自分の体質に合った飲み方やペースで、無理せずコーヒーライフを続けることが大切です。
デカフェや飲み方を工夫しながら、自分だけの最適なコーヒータイムを実現させてください!



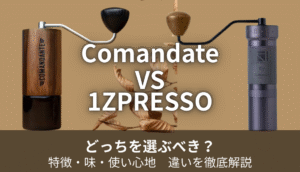
コメント